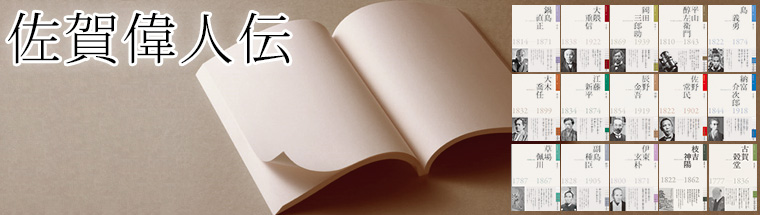2012年11月22日
東京の中の佐賀「九段」
九段
千代田区役所のはす向かい、旧千代田区役所跡地は、高齢者サポート施設や病院などを建設中と聞いています。その北側には九段会館がありました。
九段会館は、終戦までは軍人会館が置かれていた場所で、終戦後は財団法人日本遺族会が宿泊施設やレストラン、ホールなどを運営していました。しかし、東日本大震災の時に崩れた天井部材による死亡事故が起こり、現在は営業されていません。

この九段会館と旧千代田区役所の間に、小さな緑の空間があります。

そこには、いくつかの石碑が立っています。
右側の石碑には「日本体育会 体操学校之跡」とあり、ここに、現在の日本体育大学の前身である体操学校があったことを示しています。
左側の碑は「九段精華学校 発祥地」とあります。

中央の長方形の碑には、「愛國婦人會 発祥之地 小笠原長生書」と書かれていました。
小笠原長生(おがさわら ながなり、1867-1958)は、唐津藩主小笠原家の世継長行(ながみち)の長子で、子爵。海軍中将まで務め、正二位・勲一等に叙され、文筆活動も行う文化人でもありました。終生郷土のために尽力しました。

裏を見てみると、愛国婦人会の会祖奥村五百子の銅像の跡地であることを記念して、昭和30年秋の五百子の法要の日(五十回忌でしょうか)にこの碑を建てたことが記されています。
奥村五百子(おくむらいほこ、1845-1907)は、唐津に生まれ、幕末には兄の討幕運動を助けるなど、当時としては男勝りの活躍をし、その後は郷土唐津のために尽力、日清戦争後は中国、朝鮮を渡り歩き、日本軍慰問など様々な活動を行うとともに、その体験を元に明治34年愛国婦人会を設立しました。
五百子の銅像は、この場所にあったもののほか、ソウルや光州などにも建てられ、日本人女性としてはかなり多数の銅像があったようです。

そこからさらに北に歩くと九段下の交差点に出ます。この交差点の角に交番があり、その横に「蕃書調所跡」を記念する標柱と説明板がありました。

この説明板にあるように、蕃書調所は、現在の東京大学の前身です。
この蕃書調所の設立に当たったのは、古賀謹一郎(1816-1884)という人物です。古賀謹一郎は、佐賀藩の儒者で、昌平坂学問所(昌平黌)の儒官を務めた古賀精里(1750-1817)の孫に当たります。
父親は精里と同じく昌平黌の儒官を務めた古賀侗庵(とうあん、1788-1847)です。
謹一郎は、この蕃書調所の初代頭取も務めました。日本の国立大学初代総長というわけです。
参考:小野寺隆太『古賀謹一郎』ミネルヴァ書房 2006

 ぷらす
ぷらす
現在唐津大名小路二ノ門堀の近くに立っている奥村五百子像は、昭和34年に唐津市婦人連絡会によって建てられたものです。この像は、以前は、唐津城登城口南の駐車場のところにあった唐津市立体育館の前に建っていました。

千代田区役所のはす向かい、旧千代田区役所跡地は、高齢者サポート施設や病院などを建設中と聞いています。その北側には九段会館がありました。
九段会館は、終戦までは軍人会館が置かれていた場所で、終戦後は財団法人日本遺族会が宿泊施設やレストラン、ホールなどを運営していました。しかし、東日本大震災の時に崩れた天井部材による死亡事故が起こり、現在は営業されていません。

この九段会館と旧千代田区役所の間に、小さな緑の空間があります。

そこには、いくつかの石碑が立っています。
右側の石碑には「日本体育会 体操学校之跡」とあり、ここに、現在の日本体育大学の前身である体操学校があったことを示しています。
左側の碑は「九段精華学校 発祥地」とあります。

中央の長方形の碑には、「愛國婦人會 発祥之地 小笠原長生書」と書かれていました。
小笠原長生(おがさわら ながなり、1867-1958)は、唐津藩主小笠原家の世継長行(ながみち)の長子で、子爵。海軍中将まで務め、正二位・勲一等に叙され、文筆活動も行う文化人でもありました。終生郷土のために尽力しました。

裏を見てみると、愛国婦人会の会祖奥村五百子の銅像の跡地であることを記念して、昭和30年秋の五百子の法要の日(五十回忌でしょうか)にこの碑を建てたことが記されています。
奥村五百子(おくむらいほこ、1845-1907)は、唐津に生まれ、幕末には兄の討幕運動を助けるなど、当時としては男勝りの活躍をし、その後は郷土唐津のために尽力、日清戦争後は中国、朝鮮を渡り歩き、日本軍慰問など様々な活動を行うとともに、その体験を元に明治34年愛国婦人会を設立しました。
五百子の銅像は、この場所にあったもののほか、ソウルや光州などにも建てられ、日本人女性としてはかなり多数の銅像があったようです。

そこからさらに北に歩くと九段下の交差点に出ます。この交差点の角に交番があり、その横に「蕃書調所跡」を記念する標柱と説明板がありました。

この説明板にあるように、蕃書調所は、現在の東京大学の前身です。
この蕃書調所の設立に当たったのは、古賀謹一郎(1816-1884)という人物です。古賀謹一郎は、佐賀藩の儒者で、昌平坂学問所(昌平黌)の儒官を務めた古賀精里(1750-1817)の孫に当たります。
父親は精里と同じく昌平黌の儒官を務めた古賀侗庵(とうあん、1788-1847)です。
謹一郎は、この蕃書調所の初代頭取も務めました。日本の国立大学初代総長というわけです。
参考:小野寺隆太『古賀謹一郎』ミネルヴァ書房 2006

 ぷらす
ぷらす
現在唐津大名小路二ノ門堀の近くに立っている奥村五百子像は、昭和34年に唐津市婦人連絡会によって建てられたものです。この像は、以前は、唐津城登城口南の駐車場のところにあった唐津市立体育館の前に建っていました。

東京の中の佐賀「おわりに」
東京の中の佐賀「品川台場」【最終回】
東京の中の佐賀「雑司ヶ谷 納富介次郎」
東京の中の佐賀「青山霊園33 江藤新平と交わった人たち」
東京の中の佐賀「青山霊園33 高木背水・江藤淳」
東京の中の佐賀「青山霊園32 鍋島藤蔭・幹」
東京の中の佐賀「品川台場」【最終回】
東京の中の佐賀「雑司ヶ谷 納富介次郎」
東京の中の佐賀「青山霊園33 江藤新平と交わった人たち」
東京の中の佐賀「青山霊園33 高木背水・江藤淳」
東京の中の佐賀「青山霊園32 鍋島藤蔭・幹」
Posted by 佐賀城本丸歴史館 at 08:30
│東京の中の佐賀
この記事へのコメント
毎回の配信を楽しみにしている佐賀出身、埼玉在住の者です。都心に出かける際には、記事を頼りに佐賀ゆかりの場所を徘徊したりしています。
「寛政の三博士」の一人である古賀精里、やはり血は争えないといいますか、親子三代に渡って学問の世界で活躍、特に教育界で多大な貢献をしているのですね。東大の初代総長が佐賀出身というのははじめて知りました。
維新後、文部卿として現代につながる学制を整備した「七賢人」のひとり「大木喬任」が福沢諭吉らとともに「明治六大教育家」の一人として日本の教育界に名を残したり、佐賀はやはり昔から教育県なのだなあと思います。
古賀精里が中心となって設立した藩校弘道館からは、大木喬任のほか、大隈重信、江藤新平、副島種臣ら、初期の明治政府を動かした逸材を輩出しているわけです。
ちなみに、ということで、その弘道館と古賀精里のことが書かれている、現在佐賀新聞の「ひろば」欄に連載中の「撫子の賦・鍋島原田家の人々」第7回の記事をご紹介させていただきます。
http://www.facebook.com/iq002409#!/notes/%E6%B1%9F%E5%B4%8E-%E7%9F%A5%E5%85%B8/%E6%92%AB%E5%AD%90%E3%81%AE%E8%B3%A6-%E9%8D%8B%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E7%94%B0%E5%AE%B6%E3%81%AE%E4%BA%BA%E3%81%B3%E3%81%A8_no007/138539496295146
このフェイスブックの主としても、より多くの佐賀ゆかりの方々にこの連載を読んでもらいたいと言っていますので、お友達申請してみてはいかがでしょうか。
「寛政の三博士」の一人である古賀精里、やはり血は争えないといいますか、親子三代に渡って学問の世界で活躍、特に教育界で多大な貢献をしているのですね。東大の初代総長が佐賀出身というのははじめて知りました。
維新後、文部卿として現代につながる学制を整備した「七賢人」のひとり「大木喬任」が福沢諭吉らとともに「明治六大教育家」の一人として日本の教育界に名を残したり、佐賀はやはり昔から教育県なのだなあと思います。
古賀精里が中心となって設立した藩校弘道館からは、大木喬任のほか、大隈重信、江藤新平、副島種臣ら、初期の明治政府を動かした逸材を輩出しているわけです。
ちなみに、ということで、その弘道館と古賀精里のことが書かれている、現在佐賀新聞の「ひろば」欄に連載中の「撫子の賦・鍋島原田家の人々」第7回の記事をご紹介させていただきます。
http://www.facebook.com/iq002409#!/notes/%E6%B1%9F%E5%B4%8E-%E7%9F%A5%E5%85%B8/%E6%92%AB%E5%AD%90%E3%81%AE%E8%B3%A6-%E9%8D%8B%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E7%94%B0%E5%AE%B6%E3%81%AE%E4%BA%BA%E3%81%B3%E3%81%A8_no007/138539496295146
このフェイスブックの主としても、より多くの佐賀ゆかりの方々にこの連載を読んでもらいたいと言っていますので、お友達申請してみてはいかがでしょうか。
Posted by 和田直二 at 2012年11月23日 14:43
上記書き込みの追伸です。
すみません、(↑)ここからの移動はできないのですね。
フェイスブックの「江崎知典」さんにお友達申請(「佐賀ファンブログで紹介されました・・・」ということで。)していただくか、「佐賀新聞」の「記事データベース」(無料)からテキスト版を検索していただくかで、見ることができます。
>管理人様
紛らわしい部分を、削除していただければと存じます。
すみません、(↑)ここからの移動はできないのですね。
フェイスブックの「江崎知典」さんにお友達申請(「佐賀ファンブログで紹介されました・・・」ということで。)していただくか、「佐賀新聞」の「記事データベース」(無料)からテキスト版を検索していただくかで、見ることができます。
>管理人様
紛らわしい部分を、削除していただければと存じます。
Posted by 和田直二 at 2012年11月24日 11:36
いつもご覧いただきありがとうございます。
記事の部分的な削除はシステム上できません。
おゆるしください。
記事の部分的な削除はシステム上できません。
おゆるしください。
Posted by 佐賀城本丸歴史館 at 2012年12月07日 09:33
at 2012年12月07日 09:33
 at 2012年12月07日 09:33
at 2012年12月07日 09:33この記事を読んで、現地の石碑を見に行ったのですが、、、
現在、旧庁舎の建物を解体中ということで石碑を見ることが出来ませんでした。無駄足に終わってしまい非常に残念な結果になりました。
2012年11月22日の記事を読んだ事も業者の方に伝えてお願いしましたが、解体作業中で危険なので約束のない関係者以外の入場は出来ないそうです。業者の方の話では、石碑はまだ現存しているそうですが、もうずいぶん前から外部の方が見られる状態ではないそうです。せめて写真がいつの時点のものかと、現在見られるのかどうかの記載の配慮があればと思い投稿させて頂きました。同じことで悔しい思いをされる方がないことを願います。
現在、旧庁舎の建物を解体中ということで石碑を見ることが出来ませんでした。無駄足に終わってしまい非常に残念な結果になりました。
2012年11月22日の記事を読んだ事も業者の方に伝えてお願いしましたが、解体作業中で危険なので約束のない関係者以外の入場は出来ないそうです。業者の方の話では、石碑はまだ現存しているそうですが、もうずいぶん前から外部の方が見られる状態ではないそうです。せめて写真がいつの時点のものかと、現在見られるのかどうかの記載の配慮があればと思い投稿させて頂きました。同じことで悔しい思いをされる方がないことを願います。
Posted by 通りすがり at 2013年01月09日 18:14
いつも御覧頂いてありがとうございます。
御指摘のように、このブログには、最近の写真ではないものも含まれています。
個人で時間を見つけて歩いているものなので、ひとつひとつの施設の最新の状況を把握することは困難なため、中には紹介した状況と違っているものもあるかも知れません。今回の「愛国婦人会の碑」については、隣接する建物が工事中という情報はネットで確認できたため、その旨を記載しておりましたが、その工事により当該の碑が見えるのか見えないのかは確認できませんでした。
そういうわけで、ご足労をおかけして申し訳ありません。
今後は、撮影時期がわかるものについては、その時期を記載するようにします。御指摘ありがとうございました。(筆者T)
御指摘のように、このブログには、最近の写真ではないものも含まれています。
個人で時間を見つけて歩いているものなので、ひとつひとつの施設の最新の状況を把握することは困難なため、中には紹介した状況と違っているものもあるかも知れません。今回の「愛国婦人会の碑」については、隣接する建物が工事中という情報はネットで確認できたため、その旨を記載しておりましたが、その工事により当該の碑が見えるのか見えないのかは確認できませんでした。
そういうわけで、ご足労をおかけして申し訳ありません。
今後は、撮影時期がわかるものについては、その時期を記載するようにします。御指摘ありがとうございました。(筆者T)
Posted by 佐賀城本丸歴史館 at 2013年01月10日 15:58
at 2013年01月10日 15:58
 at 2013年01月10日 15:58
at 2013年01月10日 15:58