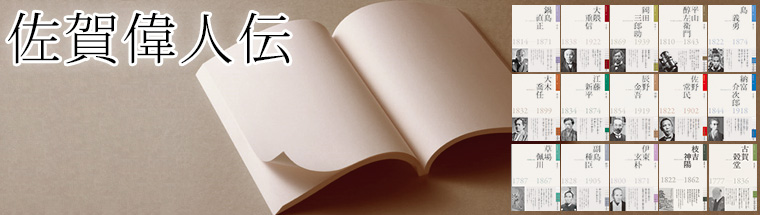2016年03月17日
東京の中の佐賀「品川台場」【最終回】
佐賀藩がわが国初めての鉄製大砲の鋳造に成功、実用化のメドが立って間もなくの嘉永6年(1853)6月、ペリー艦隊が浦賀に来航します。江戸湾防備強化の必要性に迫られた幕府は、佐賀藩に対して鉄製大砲200門の製造を打診し、佐賀藩は、50門の製造を受注しました。
佐賀藩は、この注文に応えるため、それまで大砲を鋳造していた築地の反射炉とは別に、新たに反射炉を設置することを決め、城下町多布施に、その名も「公儀石火矢鋳立所」を設置し、大砲鋳造を行いました。
幕府ではこれと並行して、品川洲崎沖から深川洲崎沖に11ヵ所の海中台場を築く計画が立てられました。

2005年3月撮影
嘉永7年12月、最終的に6基の台場が竣工しました。この間、台場建設の最大の目的であったペリーの2度目の来航を嘉永7年1月に迎え、計画は大幅に縮小されたようですが、佐賀藩は安政2年(1855)までに26門(うち8門は運送中に沈没)、安政6年(1859)までに32門が船で江戸に送られ、結果的に受注された50門すべてが幕府に納品されています。
このうち42門が品川台場に配備されました。

2009年9月撮影

2009年9月撮影

2009年9月撮影
佐賀藩は、この注文に応えるため、それまで大砲を鋳造していた築地の反射炉とは別に、新たに反射炉を設置することを決め、城下町多布施に、その名も「公儀石火矢鋳立所」を設置し、大砲鋳造を行いました。
幕府ではこれと並行して、品川洲崎沖から深川洲崎沖に11ヵ所の海中台場を築く計画が立てられました。

2005年3月撮影
嘉永7年12月、最終的に6基の台場が竣工しました。この間、台場建設の最大の目的であったペリーの2度目の来航を嘉永7年1月に迎え、計画は大幅に縮小されたようですが、佐賀藩は安政2年(1855)までに26門(うち8門は運送中に沈没)、安政6年(1859)までに32門が船で江戸に送られ、結果的に受注された50門すべてが幕府に納品されています。
このうち42門が品川台場に配備されました。

2009年9月撮影

2009年9月撮影

2009年9月撮影
東京の中の佐賀「おわりに」
東京の中の佐賀「雑司ヶ谷 納富介次郎」
東京の中の佐賀「青山霊園33 江藤新平と交わった人たち」
東京の中の佐賀「青山霊園33 高木背水・江藤淳」
東京の中の佐賀「青山霊園32 鍋島藤蔭・幹」
東京の中の佐賀「青山霊園31 中島永元」
東京の中の佐賀「雑司ヶ谷 納富介次郎」
東京の中の佐賀「青山霊園33 江藤新平と交わった人たち」
東京の中の佐賀「青山霊園33 高木背水・江藤淳」
東京の中の佐賀「青山霊園32 鍋島藤蔭・幹」
東京の中の佐賀「青山霊園31 中島永元」
Posted by 佐賀城本丸歴史館 at 08:30
│東京の中の佐賀