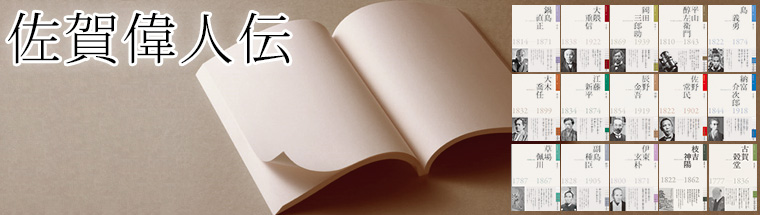2015年01月08日
東京の中の佐賀「幸龍寺 小笠原家の墓」
前回、最後の唐津藩主家である小笠原家で実際に唐津藩主を務めた9代~11代の墓がある本駒込の龍光寺を紹介しました。
今回紹介するのは、13代長国の跡を継いだ長行らの墓がある世田谷区北烏山の幸龍寺です。

2012年11月撮影
幸龍寺は、北烏丸の寺町にあります。徳川家に関係の深いお寺で、家康の江戸入府の時浜松から神田湯島に入り、後に浅草に移ったそうです。しかし関東大震災で焼失、昭和2年にこの場所で再建されたそうです。

2012年11月撮影
前回も書きましたが、唐津藩主となった小笠原家9代長昌の後は、世継ぎの男子に恵まれず、代々養子を迎えています。
そして信濃松本藩戸田光庸の子だった13代長国は、庶子として扱われていた長昌の子長行が成長したため、跡を継がせました。しかし、このことが藩内に長国派(大殿派)と長行派(若殿派)の派閥争いを巻き起こし、長国が長行を養子とすることでこの争いを鎮めたそうです。
小笠原長行(ながみち、1822-1891)は、幕末期に老中を務め、最後まで幕府側に付いたため、近隣藩から朝敵の汚名を着せられたこと等により、長行を小笠原家から義絶しています。
こうしたことから、長行を小笠原家の藩主に数えないことがあります。

2014年3月撮影
長行の子長生(ながなり、1867-1958)が、小笠原家家督を継ぎ、長生によって小笠原家の墓が建てられました。この墓には、9代長昌、13代長国、長行、14代長生らが眠っています。

2014年3月撮影
 ぷらす1
ぷらす1
龍光寺にも、幸龍寺にも墓がなかった12代長和(ながよし、1821-1840)の墓は、唐津の近松寺にありました。

2014年4月撮影

2014年4月撮影
近松寺には、小笠原家の歴史に関する展示を行った小笠原記念館が付設しています。

2014年4月撮影
 ぷらす2
ぷらす2
幸龍寺の小笠原家の墓は、当初谷中墓地に葬られていたものを移設したものです。
この墓は谷中墓地の乙4号1側にあったということを聞き、霊園の管理事務所で聞いたりして調べましたが、その跡地を特定することはできませんでした。

2012年11月撮影
今回紹介するのは、13代長国の跡を継いだ長行らの墓がある世田谷区北烏山の幸龍寺です。

2012年11月撮影
幸龍寺は、北烏丸の寺町にあります。徳川家に関係の深いお寺で、家康の江戸入府の時浜松から神田湯島に入り、後に浅草に移ったそうです。しかし関東大震災で焼失、昭和2年にこの場所で再建されたそうです。

2012年11月撮影
前回も書きましたが、唐津藩主となった小笠原家9代長昌の後は、世継ぎの男子に恵まれず、代々養子を迎えています。
そして信濃松本藩戸田光庸の子だった13代長国は、庶子として扱われていた長昌の子長行が成長したため、跡を継がせました。しかし、このことが藩内に長国派(大殿派)と長行派(若殿派)の派閥争いを巻き起こし、長国が長行を養子とすることでこの争いを鎮めたそうです。
小笠原長行(ながみち、1822-1891)は、幕末期に老中を務め、最後まで幕府側に付いたため、近隣藩から朝敵の汚名を着せられたこと等により、長行を小笠原家から義絶しています。
こうしたことから、長行を小笠原家の藩主に数えないことがあります。

2014年3月撮影
長行の子長生(ながなり、1867-1958)が、小笠原家家督を継ぎ、長生によって小笠原家の墓が建てられました。この墓には、9代長昌、13代長国、長行、14代長生らが眠っています。

2014年3月撮影
 ぷらす1
ぷらす1
龍光寺にも、幸龍寺にも墓がなかった12代長和(ながよし、1821-1840)の墓は、唐津の近松寺にありました。

2014年4月撮影

2014年4月撮影
近松寺には、小笠原家の歴史に関する展示を行った小笠原記念館が付設しています。

2014年4月撮影
 ぷらす2
ぷらす2
幸龍寺の小笠原家の墓は、当初谷中墓地に葬られていたものを移設したものです。
この墓は谷中墓地の乙4号1側にあったということを聞き、霊園の管理事務所で聞いたりして調べましたが、その跡地を特定することはできませんでした。

2012年11月撮影
東京の中の佐賀「おわりに」
東京の中の佐賀「品川台場」【最終回】
東京の中の佐賀「雑司ヶ谷 納富介次郎」
東京の中の佐賀「青山霊園33 江藤新平と交わった人たち」
東京の中の佐賀「青山霊園33 高木背水・江藤淳」
東京の中の佐賀「青山霊園32 鍋島藤蔭・幹」
東京の中の佐賀「品川台場」【最終回】
東京の中の佐賀「雑司ヶ谷 納富介次郎」
東京の中の佐賀「青山霊園33 江藤新平と交わった人たち」
東京の中の佐賀「青山霊園33 高木背水・江藤淳」
東京の中の佐賀「青山霊園32 鍋島藤蔭・幹」
Posted by 佐賀城本丸歴史館 at 08:30
│東京の中の佐賀