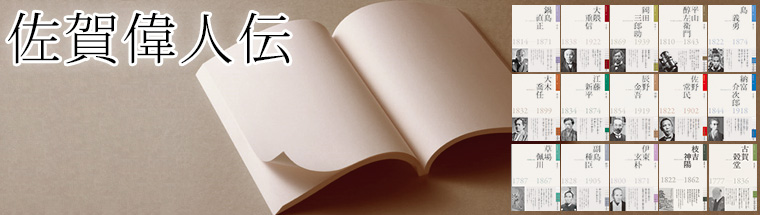2014年01月23日
東京の中の佐賀「久米美術館・林試の森」
目黒駅のホームから見上げると、久米美術館がある久米ビルが見えました。

2007年11月撮影
久米美術館は、久米ビルの8階にあります。

2008年10月撮影
久米ビルの、美術館専用のエレベーター入り口の前では、久米邦武の銅像が出迎えてくれました。
美術館のある8階には邦武の子桂一郎の銅像がありました。
この美術館では、邦武や桂一郎の業績を展示するほか、時々企画展として近代日本美術や近代史に関する展示などが行われています。

2011年11月撮影
久米 邦武(1839- 1931)は、近代歴史学の基礎を築きました。幕末の佐賀藩士で、25歳で江戸に出て昌平黌で学び、新政府になると、明治4年岩倉具視に従い欧米を視察し、帰国後『米欧回覧実記』を編纂しました。その後、帝国大学教授等に就任し、日本古代史の科学的研究の先鞭をつけましたが、論文「神道は祭天の古俗」が不敬であるとして糾弾を受け、大学の職を辞しました。
久米 桂一郎(1866 - 1934)は、邦武の子で、佐賀城下に生まれました。明治19年に絵画修業のため私費でフランスに渡り、黒田清輝とともに学びました。帰国後、日本の美術界を先導し、のち東京美術学校の西洋画科で後進の指導に当たりました。
この場所に久米美術館が建てられたのには理由があります。
邦武が『米欧回覧実記』編修を行った功に対し、政府から500円が下賜され、これを基に鍋島家の「鍋島苗圃」という農園があったこの一帯の土地を購入しました。この場所からみる富士の見晴らしが良かったからだそうです。
邦武は、ここを京橋の本邸とは別に「林間の山荘」として利用したそうです。
その面影を残す場所として、現在林試の森という森林公園がある付近も、邦武が購入した土地の一部だそうで、人を雇い自ら指揮して畑を耕し、麦作をしたりしたそうです。

2008年10月撮影

2008年10月撮影

2007年11月撮影
久米美術館は、久米ビルの8階にあります。

2008年10月撮影
久米ビルの、美術館専用のエレベーター入り口の前では、久米邦武の銅像が出迎えてくれました。
美術館のある8階には邦武の子桂一郎の銅像がありました。
この美術館では、邦武や桂一郎の業績を展示するほか、時々企画展として近代日本美術や近代史に関する展示などが行われています。

2011年11月撮影
久米 邦武(1839- 1931)は、近代歴史学の基礎を築きました。幕末の佐賀藩士で、25歳で江戸に出て昌平黌で学び、新政府になると、明治4年岩倉具視に従い欧米を視察し、帰国後『米欧回覧実記』を編纂しました。その後、帝国大学教授等に就任し、日本古代史の科学的研究の先鞭をつけましたが、論文「神道は祭天の古俗」が不敬であるとして糾弾を受け、大学の職を辞しました。
久米 桂一郎(1866 - 1934)は、邦武の子で、佐賀城下に生まれました。明治19年に絵画修業のため私費でフランスに渡り、黒田清輝とともに学びました。帰国後、日本の美術界を先導し、のち東京美術学校の西洋画科で後進の指導に当たりました。
この場所に久米美術館が建てられたのには理由があります。
邦武が『米欧回覧実記』編修を行った功に対し、政府から500円が下賜され、これを基に鍋島家の「鍋島苗圃」という農園があったこの一帯の土地を購入しました。この場所からみる富士の見晴らしが良かったからだそうです。
邦武は、ここを京橋の本邸とは別に「林間の山荘」として利用したそうです。
その面影を残す場所として、現在林試の森という森林公園がある付近も、邦武が購入した土地の一部だそうで、人を雇い自ら指揮して畑を耕し、麦作をしたりしたそうです。

2008年10月撮影

2008年10月撮影
東京の中の佐賀「おわりに」
東京の中の佐賀「品川台場」【最終回】
東京の中の佐賀「雑司ヶ谷 納富介次郎」
東京の中の佐賀「青山霊園33 江藤新平と交わった人たち」
東京の中の佐賀「青山霊園33 高木背水・江藤淳」
東京の中の佐賀「青山霊園32 鍋島藤蔭・幹」
東京の中の佐賀「品川台場」【最終回】
東京の中の佐賀「雑司ヶ谷 納富介次郎」
東京の中の佐賀「青山霊園33 江藤新平と交わった人たち」
東京の中の佐賀「青山霊園33 高木背水・江藤淳」
東京の中の佐賀「青山霊園32 鍋島藤蔭・幹」
Posted by 佐賀城本丸歴史館 at 08:30
│東京の中の佐賀