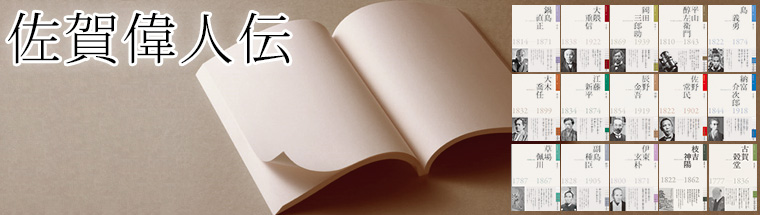2013年07月25日
東京の中の佐賀「青山霊園6 田中儀右衛門」」
田中久重(1799-1881)は、久留米藩士で、幼い時からからくり人形などに興味を持ち、長じてさまざまな機械仕掛けに挑戦、「からくり儀右衛門」として、世に名を知られました。
久重の才能に注目した佐賀藩士佐野常民は、彼を佐賀に連れ帰り、鍋島直正のもと、西洋の近代技術を学ぶ精煉方に着任させました。久重は、蒸気機関車や蒸気船の模型を製造、反射炉の設計(改築)と大砲製造に貢献しました。また、文久元年には佐賀藩の三重津海軍所で藩の蒸気船「電流丸」の蒸気罐製造担当者となっているほか、文久3年には実用的に運用された国産初の蒸気船である「凌風丸」建造に加わっています。
久重は、久留米に帰藩したのち、晩年の明治6年(1873年)に上京。電信機関係の製作所・田中製造所を設立、これが現在の東芝の基礎となっています。

2013年1月撮影
田中久重の墓は、1種ロ12号31側10番にあります。
田中家の墓は近年かなり様変わりしました。墓地も年とともに変化するのです。(かつての姿を写真に撮っていなかったのは残念です。)

2013年1月撮影
田中久重と配(配偶者)與志子の墓です。久重の後を継いだ二世田中久重(1846-1905)が建立したものです。

2013年1月撮影
その向かいには、二世久重と配美知恵の墓がありました。

2013年1月撮影
墓域入り口には、左右に黒御影石の碑があり、右の碑には田中久重の事蹟など、左の碑には、「万般の機械 考案の依頼に応ず」という言葉と、久重翁の肖像を描いています。この言葉は、明治8年に田中久重が東芝の礎となった現在の銀座8丁目に店舗兼住居を構えた時、掲げた看板に記されていたそうです。

2007年6月撮影
佐野の斡旋により佐賀藩に着任した久重には、久重に才能を見込まれて久重の養子となっていた儀右衛門(重儀、1818?-1863)も同行していました。
この養子儀右衛門も、技工に長じており、元治元年(1864)、父久重が久留米藩に召し抱えられると、佐賀の方はこの儀右衛門が専任となっています。しかし、精神に異常を来したある藩士により、彼は、息子岩次郎(1847?-1863)と共に斬殺されてしまいます。藩主直正は、その最期を悼み、久重とともに佐賀藩に呼ばれて精煉方で技術者を務めていた中村奇輔(1825-1876)の二男林太郎(1855?-1924)を養子として跡をつがせ、士籍に列しました。 この墓は、林太郎が父儀右衛門、母美津子(1823?-1886)、兄岩次郎らを弔うために立てた一族の墓です。「佐賀県士族田中氏之墓」とあります。
この墓は1種イ 6号1側にありました。

2013年4月撮影
 ぷらす1
ぷらす1
田中儀右衛門の墓が、築地反射炉跡のすぐ近くにある佐賀市天佑寺にあります。

2013年6月撮影
墓の裏には「田中儀右衛門重久」と刻まれています。久重の養子儀右衛門の墓なのでしょうか。

2013年6月撮影
 ぷらす2
ぷらす2
田中儀右衛門久重の生誕地跡は、久留米市通外十丁目にありました。鉄道の高架事業で少し場所が動いたそうです。

2013年3月撮影
久重の才能に注目した佐賀藩士佐野常民は、彼を佐賀に連れ帰り、鍋島直正のもと、西洋の近代技術を学ぶ精煉方に着任させました。久重は、蒸気機関車や蒸気船の模型を製造、反射炉の設計(改築)と大砲製造に貢献しました。また、文久元年には佐賀藩の三重津海軍所で藩の蒸気船「電流丸」の蒸気罐製造担当者となっているほか、文久3年には実用的に運用された国産初の蒸気船である「凌風丸」建造に加わっています。
久重は、久留米に帰藩したのち、晩年の明治6年(1873年)に上京。電信機関係の製作所・田中製造所を設立、これが現在の東芝の基礎となっています。

2013年1月撮影
田中久重の墓は、1種ロ12号31側10番にあります。
田中家の墓は近年かなり様変わりしました。墓地も年とともに変化するのです。(かつての姿を写真に撮っていなかったのは残念です。)

2013年1月撮影
田中久重と配(配偶者)與志子の墓です。久重の後を継いだ二世田中久重(1846-1905)が建立したものです。

2013年1月撮影
その向かいには、二世久重と配美知恵の墓がありました。

2013年1月撮影
墓域入り口には、左右に黒御影石の碑があり、右の碑には田中久重の事蹟など、左の碑には、「万般の機械 考案の依頼に応ず」という言葉と、久重翁の肖像を描いています。この言葉は、明治8年に田中久重が東芝の礎となった現在の銀座8丁目に店舗兼住居を構えた時、掲げた看板に記されていたそうです。

2007年6月撮影
佐野の斡旋により佐賀藩に着任した久重には、久重に才能を見込まれて久重の養子となっていた儀右衛門(重儀、1818?-1863)も同行していました。
この養子儀右衛門も、技工に長じており、元治元年(1864)、父久重が久留米藩に召し抱えられると、佐賀の方はこの儀右衛門が専任となっています。しかし、精神に異常を来したある藩士により、彼は、息子岩次郎(1847?-1863)と共に斬殺されてしまいます。藩主直正は、その最期を悼み、久重とともに佐賀藩に呼ばれて精煉方で技術者を務めていた中村奇輔(1825-1876)の二男林太郎(1855?-1924)を養子として跡をつがせ、士籍に列しました。 この墓は、林太郎が父儀右衛門、母美津子(1823?-1886)、兄岩次郎らを弔うために立てた一族の墓です。「佐賀県士族田中氏之墓」とあります。
この墓は1種イ 6号1側にありました。

2013年4月撮影
 ぷらす1
ぷらす1
田中儀右衛門の墓が、築地反射炉跡のすぐ近くにある佐賀市天佑寺にあります。

2013年6月撮影
墓の裏には「田中儀右衛門重久」と刻まれています。久重の養子儀右衛門の墓なのでしょうか。

2013年6月撮影
 ぷらす2
ぷらす2
田中儀右衛門久重の生誕地跡は、久留米市通外十丁目にありました。鉄道の高架事業で少し場所が動いたそうです。

2013年3月撮影
東京の中の佐賀「おわりに」
東京の中の佐賀「品川台場」【最終回】
東京の中の佐賀「雑司ヶ谷 納富介次郎」
東京の中の佐賀「青山霊園33 江藤新平と交わった人たち」
東京の中の佐賀「青山霊園33 高木背水・江藤淳」
東京の中の佐賀「青山霊園32 鍋島藤蔭・幹」
東京の中の佐賀「品川台場」【最終回】
東京の中の佐賀「雑司ヶ谷 納富介次郎」
東京の中の佐賀「青山霊園33 江藤新平と交わった人たち」
東京の中の佐賀「青山霊園33 高木背水・江藤淳」
東京の中の佐賀「青山霊園32 鍋島藤蔭・幹」
Posted by 佐賀城本丸歴史館 at 08:30
│東京の中の佐賀