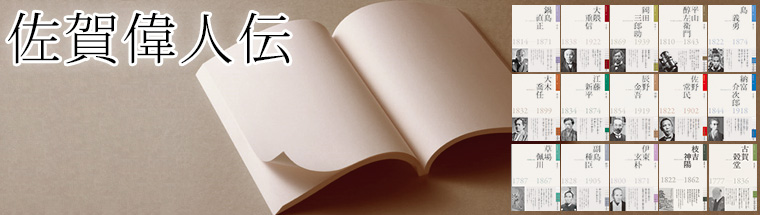2013年05月02日
東京の中の佐賀「神宮外苑」
日本青年館は、ホテルやホールなどが運営される複合施設ですが、日本における青年団活動の総本山としての性格も持っていました。
青年館が、ここ明治神宮外苑に所在することは偶然ではありません。明治神宮の造営に勤労奉仕をした青年団が皇太子から功績をたたえられたことを記念して、大正9年(1920)に建設が提案され、1人1円を合い言葉に全国の青年団員による募金活動などにより、大正11年(1922)着工、大正14年に初代の日本青年館が完成しました。
先に紹介した小金井市の「浴恩館」は、この日本青年館の別館として、青年団指導者養成のために設置された施設です。

2012年11月撮影
現在の建物は、昭和54年に改築されました。

2012年11月撮影
この明治神宮の創建にあたって、青年団員による協力を提案し、これを実行したのが、かねてより青年団運動の必要性を訴えていた、佐賀県鹿島市出身の田澤 義鋪(たざわ よしはる、1885-1944)です。
1926年(大正15年・昭和元年)、田澤は完成した日本青年館ならびに大日本連合青年団の常任理事に就任しました。
現在の青年館の1階ロビーには、田澤義鋪と、同じく青年館設立に助力し、理事長も務めた後藤文夫像が置かれています。

2012年11月撮影
右が、田澤の像です。台座に「昭和三十五年十月廿六日序幕/財團法人田澤義鋪記念會」とありました。

2012年11月撮影
聖徳記念絵画館は、明治神宮造営にあたって、その中心的な建物として建築されました。
この建物は、平成23年(2011)に、「直線的意匠と先駆的技術を採用した、わが国初期の美術館建築」と評価され、明治神宮宝物館とともに国の重要文化財に指定されました。

2013年4月撮影
聖徳記念絵画館には、当代一流の画家らが、史実に基づく明治天皇と昭憲皇后の遺徳を描いた絵画が年代順に展示されています。

2013年4月撮影
館内の写真撮影はできませんでしたが、80枚の壁画のうち、14番目の「大阪行幸諸藩軍艦御覧」は、佐賀県出身の洋画家 岡田三郎助が描いたもので、侯爵 鍋島直映の奉納によるものです。
この絵は、インターネットでも公開されているので見ていただきたいと思いますが、明治元年3月に、佐賀藩の軍艦電流丸に鍋島直大らが乗り、諸藩の軍艦を率いて天皇をお迎えする模様を描いたものです。わが国観艦式のはじまりとされています。
青年館が、ここ明治神宮外苑に所在することは偶然ではありません。明治神宮の造営に勤労奉仕をした青年団が皇太子から功績をたたえられたことを記念して、大正9年(1920)に建設が提案され、1人1円を合い言葉に全国の青年団員による募金活動などにより、大正11年(1922)着工、大正14年に初代の日本青年館が完成しました。
先に紹介した小金井市の「浴恩館」は、この日本青年館の別館として、青年団指導者養成のために設置された施設です。

2012年11月撮影
現在の建物は、昭和54年に改築されました。

2012年11月撮影
この明治神宮の創建にあたって、青年団員による協力を提案し、これを実行したのが、かねてより青年団運動の必要性を訴えていた、佐賀県鹿島市出身の田澤 義鋪(たざわ よしはる、1885-1944)です。
1926年(大正15年・昭和元年)、田澤は完成した日本青年館ならびに大日本連合青年団の常任理事に就任しました。
現在の青年館の1階ロビーには、田澤義鋪と、同じく青年館設立に助力し、理事長も務めた後藤文夫像が置かれています。

2012年11月撮影
右が、田澤の像です。台座に「昭和三十五年十月廿六日序幕/財團法人田澤義鋪記念會」とありました。

2012年11月撮影
聖徳記念絵画館は、明治神宮造営にあたって、その中心的な建物として建築されました。
この建物は、平成23年(2011)に、「直線的意匠と先駆的技術を採用した、わが国初期の美術館建築」と評価され、明治神宮宝物館とともに国の重要文化財に指定されました。

2013年4月撮影
聖徳記念絵画館には、当代一流の画家らが、史実に基づく明治天皇と昭憲皇后の遺徳を描いた絵画が年代順に展示されています。

2013年4月撮影
館内の写真撮影はできませんでしたが、80枚の壁画のうち、14番目の「大阪行幸諸藩軍艦御覧」は、佐賀県出身の洋画家 岡田三郎助が描いたもので、侯爵 鍋島直映の奉納によるものです。
この絵は、インターネットでも公開されているので見ていただきたいと思いますが、明治元年3月に、佐賀藩の軍艦電流丸に鍋島直大らが乗り、諸藩の軍艦を率いて天皇をお迎えする模様を描いたものです。わが国観艦式のはじまりとされています。
東京の中の佐賀「おわりに」
東京の中の佐賀「品川台場」【最終回】
東京の中の佐賀「雑司ヶ谷 納富介次郎」
東京の中の佐賀「青山霊園33 江藤新平と交わった人たち」
東京の中の佐賀「青山霊園33 高木背水・江藤淳」
東京の中の佐賀「青山霊園32 鍋島藤蔭・幹」
東京の中の佐賀「品川台場」【最終回】
東京の中の佐賀「雑司ヶ谷 納富介次郎」
東京の中の佐賀「青山霊園33 江藤新平と交わった人たち」
東京の中の佐賀「青山霊園33 高木背水・江藤淳」
東京の中の佐賀「青山霊園32 鍋島藤蔭・幹」
Posted by 佐賀城本丸歴史館 at 08:30
│東京の中の佐賀
この記事へのコメント
この企画面白いですね。大木や副島の墓は実際に訪れました。次回は久米美術館や賢崇寺などを取り上げてみてはいかがでしょうか?
Posted by 佐賀出身のとある早大生 at 2013年05月30日 19:08
かつて、外苑長を務めた伊丹安廣さんも佐賀出身ですね。
旧姓佐賀中学から早稲田大学に進み名捕手として鳴らしたあと、
野球部の6代監督を務め、その後社会人野球などアマチュア球界
発展の功績により野殿堂入りした人です。
http://db.saga-s.co.jp/opendb/2012/10/14/096_09.html
一昨年10月ごろから約一年かけて58回にわたって佐賀新聞に掲載された
「撫子の賦、原田家の人々」の第2回めに、そのことが掲載されています。
※鍋島原田家は、幕末に鍋島閑叟付の名執政として活躍した原田小四郎を出した原田家の歴史物語です。
旧姓佐賀中学から早稲田大学に進み名捕手として鳴らしたあと、
野球部の6代監督を務め、その後社会人野球などアマチュア球界
発展の功績により野殿堂入りした人です。
http://db.saga-s.co.jp/opendb/2012/10/14/096_09.html
一昨年10月ごろから約一年かけて58回にわたって佐賀新聞に掲載された
「撫子の賦、原田家の人々」の第2回めに、そのことが掲載されています。
※鍋島原田家は、幕末に鍋島閑叟付の名執政として活躍した原田小四郎を出した原田家の歴史物語です。
Posted by 和田直二 at 2014年02月20日 09:53
上記のURLからは読みにいけませんでしたね。
以下に記事を転載しておきます。
//////////////////////////////////////////////////////////
旧制佐賀中学のOBで、日本学生野球協会の常任理事だった牟田正孝さんによれば、旧制佐賀中学野球部の公式ユニホームには大正9年(1920)まで「SAGA」の文字が記されていた。翌大正10年、ユニホームの胸マークの文字は「SAGA」から「EIJO」に変更されている。
変更のきっかけとなったのは、一篇の漢詩だった。「百尺老楠蔭一郷 参天蟠地幾千霜 慶天昌運天初定 城係栄名日月長」
高さ百尺ほどもある楠の大木が一郷に蔭をつくっている。天にもとどき、その根は地に深く張り、幾千年も経た老大木だ。慶長、元和年間になって、徳川幕府の運勢もここにはじめて安定した。佐嘉(さか)の城も栄(さかえ)城と名づけて、日月が無窮なようにいつまでも栄えるだろう、といった意味だ。
漢詩は、当時の国漢教科書の副読本『豫章』に掲載されていた。漢詩の題は『栄城(さかえじょう)』。ちなみに『豫章』の「豫」は中国の南部の江西省をさし、「章」は樟(くすのき)を意味する。
この漢詩に心を動かされたのが、当時の旧制佐賀中学野球部の主将、伊丹安廣さんだ。伊丹さんは栄城にあやかってユニホームの胸マークの変更を熱望、大正10年、彼の思いは実現し、ユニホームの胸マークの文字が「SAGA」から栄城を音読みし英文字にした「EIJO」に変更されたという。
伊丹さんは旧制佐賀中学から早稲田に進んで名捕手として鳴らし、早稲田大学野球部の第6代監督に就任、社会人野球の監督も歴任、アマ球界での功績が認められ野球殿堂入りを果たした。後年、学生野球の聖地、神宮球場を管理する神宮外苑の外苑長となる。
伊丹さんの心を動かした漢詩『栄城』の作者は、泰長院に眠る高名な儒学者にして、藩校・弘道館の教師だった原田復初(ふくしょ)である。
ユニホームの「EIJO」の胸のマークは旧制佐賀中学から戦後の新制佐賀高校に継がれ、昭和38(1963)年、佐賀高校の三校分離によって誕生した佐賀西高に受け継がれた。佐中、佐高、西高の同窓会も「栄城会」といい、私は「EIJO」の流れをくむ佐賀西高の一期生にあたる。原田復初の没後、170余年がたつが、復初が今も生きているというゆえんである。
この物語は5月中旬、東京・本郷の自宅に届いた一通の手紙からはじまる。
以下に記事を転載しておきます。
//////////////////////////////////////////////////////////
旧制佐賀中学のOBで、日本学生野球協会の常任理事だった牟田正孝さんによれば、旧制佐賀中学野球部の公式ユニホームには大正9年(1920)まで「SAGA」の文字が記されていた。翌大正10年、ユニホームの胸マークの文字は「SAGA」から「EIJO」に変更されている。
変更のきっかけとなったのは、一篇の漢詩だった。「百尺老楠蔭一郷 参天蟠地幾千霜 慶天昌運天初定 城係栄名日月長」
高さ百尺ほどもある楠の大木が一郷に蔭をつくっている。天にもとどき、その根は地に深く張り、幾千年も経た老大木だ。慶長、元和年間になって、徳川幕府の運勢もここにはじめて安定した。佐嘉(さか)の城も栄(さかえ)城と名づけて、日月が無窮なようにいつまでも栄えるだろう、といった意味だ。
漢詩は、当時の国漢教科書の副読本『豫章』に掲載されていた。漢詩の題は『栄城(さかえじょう)』。ちなみに『豫章』の「豫」は中国の南部の江西省をさし、「章」は樟(くすのき)を意味する。
この漢詩に心を動かされたのが、当時の旧制佐賀中学野球部の主将、伊丹安廣さんだ。伊丹さんは栄城にあやかってユニホームの胸マークの変更を熱望、大正10年、彼の思いは実現し、ユニホームの胸マークの文字が「SAGA」から栄城を音読みし英文字にした「EIJO」に変更されたという。
伊丹さんは旧制佐賀中学から早稲田に進んで名捕手として鳴らし、早稲田大学野球部の第6代監督に就任、社会人野球の監督も歴任、アマ球界での功績が認められ野球殿堂入りを果たした。後年、学生野球の聖地、神宮球場を管理する神宮外苑の外苑長となる。
伊丹さんの心を動かした漢詩『栄城』の作者は、泰長院に眠る高名な儒学者にして、藩校・弘道館の教師だった原田復初(ふくしょ)である。
ユニホームの「EIJO」の胸のマークは旧制佐賀中学から戦後の新制佐賀高校に継がれ、昭和38(1963)年、佐賀高校の三校分離によって誕生した佐賀西高に受け継がれた。佐中、佐高、西高の同窓会も「栄城会」といい、私は「EIJO」の流れをくむ佐賀西高の一期生にあたる。原田復初の没後、170余年がたつが、復初が今も生きているというゆえんである。
この物語は5月中旬、東京・本郷の自宅に届いた一通の手紙からはじまる。
Posted by 和田直二 at 2014年02月20日 10:05
伊丹さんの出身は四国の香川県でした。
父親の赴任先だったとか、どのような事情があったのか?
あるいは、憧れ(小学生が?)があって、単身香川県からわざわざ佐賀なのか?
いずれにしても、佐賀中学出身ということは間違いありません。
父親の赴任先だったとか、どのような事情があったのか?
あるいは、憧れ(小学生が?)があって、単身香川県からわざわざ佐賀なのか?
いずれにしても、佐賀中学出身ということは間違いありません。
Posted by 和田直二 at 2014年03月11日 00:13