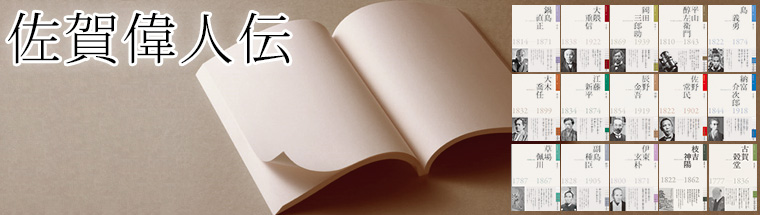2013年01月24日
東京の中の佐賀「大塚・先儒墓所」
大塚先儒墓所は、徳川家に仕えた儒者たちの墓地です。
この墓所の入り口は通常鍵がかかっており、その鍵は近くの吹上稲荷神社が管理されています。

2008年11月撮影
宅地の間にある「大塚先儒墓所」と書かれた道を進み、階段の入り口の扉を鍵で開いて、階段を上っていくと、大塚先儒墓所があります。

2008年11月撮影
大塚先儒墓所は、仏式で葬儀することが体面上からも憚られる昌平黌の朱子学教官である柴野栗山、尾藤二洲らが幕府に願い出て、儒式の葬儀による墓地を設けたものだそうです。
遅れて教官になった佐賀藩出身の古賀精里は、二洲から土地を借りて埋葬地としたとのことです。
この墓所は、国の史跡に指定されています。

2008年11月撮影
柴野家、尾藤家の墓碑群を右手にしながら進むと、一番奥の墓碑群が古賀家の墓所となっています。

2008年11月撮影
古賀精里の墓です。
古賀 精里(1750-1817)は、佐賀藩に生まれ、京都の横井小車や西依成斎に学び、大坂に塾を開きます。その後帰藩して藩主鍋島治茂に仕え、1781年に藩校・弘道館が設立されるとその教授となり、その基礎を築きました。
1796年、47歳の時、幕府に招聘されて昌平黌の儒官となり、柴野栗山・尾藤二洲とともに寛政の三博士といわれます。

2008年11月撮影
古賀侗庵の墓です。
古賀侗庵(1788-1847)は、古賀精里の三男で、佐賀に生まれましたが、9歳で父に伴われて江戸に出、22歳で幕府の御儒者見習、30歳で御儒者となり、昌平黌で教鞭を執ります。海防に意を注ぎ、39歳の時千島列島のウルップや択捉まで3年間調査をし、いち早く開港論を唱えます。

2008年11月撮影
古賀茶渓、通称謹一郎(1816-1884)については、本ブログ11月22日号で紹介しました。
古賀侗庵の子で、昌平黌の儒官の後、蕃書調所の設立、初代頭取を務めました。

2008年11月撮影
 ぷらす
ぷらす
古賀精里の長男古賀穀堂(1778-1836)は、20歳の時精里に伴われて江戸に出、柴野栗山や尾藤二洲らと交わりますが、その後佐賀に戻り弘道館の教授となります。藩主の信任が厚く、藩政に参与し、穀堂が著した『済急封事』は、幕末佐賀藩の進み方を方向付けたと云われています。
古賀家の墓所は、佐賀市金立町大門にあります。

2013年1月撮影
古賀穀堂の墓です。

2013年1月撮影
この墓所の入り口は通常鍵がかかっており、その鍵は近くの吹上稲荷神社が管理されています。

2008年11月撮影
宅地の間にある「大塚先儒墓所」と書かれた道を進み、階段の入り口の扉を鍵で開いて、階段を上っていくと、大塚先儒墓所があります。

2008年11月撮影
大塚先儒墓所は、仏式で葬儀することが体面上からも憚られる昌平黌の朱子学教官である柴野栗山、尾藤二洲らが幕府に願い出て、儒式の葬儀による墓地を設けたものだそうです。
遅れて教官になった佐賀藩出身の古賀精里は、二洲から土地を借りて埋葬地としたとのことです。
この墓所は、国の史跡に指定されています。

2008年11月撮影
柴野家、尾藤家の墓碑群を右手にしながら進むと、一番奥の墓碑群が古賀家の墓所となっています。

2008年11月撮影
古賀精里の墓です。
古賀 精里(1750-1817)は、佐賀藩に生まれ、京都の横井小車や西依成斎に学び、大坂に塾を開きます。その後帰藩して藩主鍋島治茂に仕え、1781年に藩校・弘道館が設立されるとその教授となり、その基礎を築きました。
1796年、47歳の時、幕府に招聘されて昌平黌の儒官となり、柴野栗山・尾藤二洲とともに寛政の三博士といわれます。

2008年11月撮影
古賀侗庵の墓です。
古賀侗庵(1788-1847)は、古賀精里の三男で、佐賀に生まれましたが、9歳で父に伴われて江戸に出、22歳で幕府の御儒者見習、30歳で御儒者となり、昌平黌で教鞭を執ります。海防に意を注ぎ、39歳の時千島列島のウルップや択捉まで3年間調査をし、いち早く開港論を唱えます。

2008年11月撮影
古賀茶渓、通称謹一郎(1816-1884)については、本ブログ11月22日号で紹介しました。
古賀侗庵の子で、昌平黌の儒官の後、蕃書調所の設立、初代頭取を務めました。

2008年11月撮影
 ぷらす
ぷらす
古賀精里の長男古賀穀堂(1778-1836)は、20歳の時精里に伴われて江戸に出、柴野栗山や尾藤二洲らと交わりますが、その後佐賀に戻り弘道館の教授となります。藩主の信任が厚く、藩政に参与し、穀堂が著した『済急封事』は、幕末佐賀藩の進み方を方向付けたと云われています。
古賀家の墓所は、佐賀市金立町大門にあります。

2013年1月撮影
古賀穀堂の墓です。

2013年1月撮影
東京の中の佐賀「おわりに」
東京の中の佐賀「品川台場」【最終回】
東京の中の佐賀「雑司ヶ谷 納富介次郎」
東京の中の佐賀「青山霊園33 江藤新平と交わった人たち」
東京の中の佐賀「青山霊園33 高木背水・江藤淳」
東京の中の佐賀「青山霊園32 鍋島藤蔭・幹」
東京の中の佐賀「品川台場」【最終回】
東京の中の佐賀「雑司ヶ谷 納富介次郎」
東京の中の佐賀「青山霊園33 江藤新平と交わった人たち」
東京の中の佐賀「青山霊園33 高木背水・江藤淳」
東京の中の佐賀「青山霊園32 鍋島藤蔭・幹」
Posted by 佐賀城本丸歴史館 at 08:30
│東京の中の佐賀