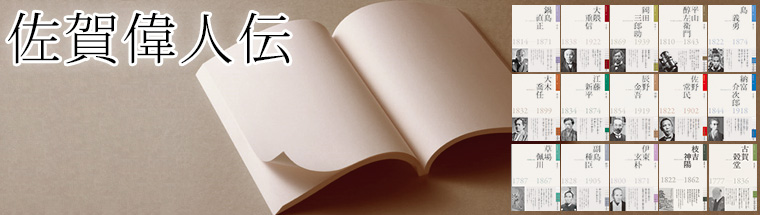2012年10月11日
東京の中の佐賀「日比谷公園辺り」
日比谷公園辺り
法務省赤れんが館(法務省旧本館)の東には日比谷公園があります。千代田区民の憩いの広場であるとともに、官庁街にある緑の森とも言えます。

広場にある説明板によると、この公園は明治36年6月に日本初の洋風公園として開園しました。
ここは幕末まで松平肥前守、すなわち佐賀鍋島藩の江戸屋敷などがあった場所と書かれてあります。その後、陸軍近衛師団の練兵場になったようです。
佐賀藩上屋敷の西隣には、長州毛利藩の屋敷がありました。
また、南西側には、江戸後期に唐津藩の大名であった小笠原佐渡守の屋敷もありました。小笠原家の屋敷も現在の日比谷公園付近にありました。

さらに、佐賀藩の屋敷の南西方、現在の帝国ホテルのある辺りには、幕末には鍋島加賀守、すなわち小城藩鍋島直亮(なおすけ)、その子直虎の上屋敷がありました。

佐賀藩江戸上屋敷は、歌川広重作『名所江戸百景』のうちの一景 「山下町 日比谷外 さくら田」に描かれている屋敷です。
当時のこの周辺の風景を偲ぶよすがとして、日比谷見附の石垣や、濠の名残の池(心字池)などがあります。


石垣の上に上ると、江戸城(皇居)の濠と石垣が見えます。

公園の南側には、大正12年に完成した野外音楽堂があり、その南西隅に、かもめの広場という小公園がありますが、その中にも「郷土の森」がありました。
先に国会議事堂の中で見たような各県の県木でできた森です。(ここには、政令指定都市から寄贈された木もあります。)佐賀県のクスノキは「41番」、赤い矢印を付けた場所にありました。

こちらのクスノキは国会のものより、もっと大木になっています。それぞれの木が大きくなっていった時、どの木を残すか問題になりそうな予感がします。

法務省赤れんが館(法務省旧本館)の東には日比谷公園があります。千代田区民の憩いの広場であるとともに、官庁街にある緑の森とも言えます。

広場にある説明板によると、この公園は明治36年6月に日本初の洋風公園として開園しました。
ここは幕末まで松平肥前守、すなわち佐賀鍋島藩の江戸屋敷などがあった場所と書かれてあります。その後、陸軍近衛師団の練兵場になったようです。
佐賀藩上屋敷の西隣には、長州毛利藩の屋敷がありました。
また、南西側には、江戸後期に唐津藩の大名であった小笠原佐渡守の屋敷もありました。小笠原家の屋敷も現在の日比谷公園付近にありました。

さらに、佐賀藩の屋敷の南西方、現在の帝国ホテルのある辺りには、幕末には鍋島加賀守、すなわち小城藩鍋島直亮(なおすけ)、その子直虎の上屋敷がありました。

佐賀藩江戸上屋敷は、歌川広重作『名所江戸百景』のうちの一景 「山下町 日比谷外 さくら田」に描かれている屋敷です。
当時のこの周辺の風景を偲ぶよすがとして、日比谷見附の石垣や、濠の名残の池(心字池)などがあります。


石垣の上に上ると、江戸城(皇居)の濠と石垣が見えます。

公園の南側には、大正12年に完成した野外音楽堂があり、その南西隅に、かもめの広場という小公園がありますが、その中にも「郷土の森」がありました。
先に国会議事堂の中で見たような各県の県木でできた森です。(ここには、政令指定都市から寄贈された木もあります。)佐賀県のクスノキは「41番」、赤い矢印を付けた場所にありました。

こちらのクスノキは国会のものより、もっと大木になっています。それぞれの木が大きくなっていった時、どの木を残すか問題になりそうな予感がします。

東京の中の佐賀「おわりに」
東京の中の佐賀「品川台場」【最終回】
東京の中の佐賀「雑司ヶ谷 納富介次郎」
東京の中の佐賀「青山霊園33 江藤新平と交わった人たち」
東京の中の佐賀「青山霊園33 高木背水・江藤淳」
東京の中の佐賀「青山霊園32 鍋島藤蔭・幹」
東京の中の佐賀「品川台場」【最終回】
東京の中の佐賀「雑司ヶ谷 納富介次郎」
東京の中の佐賀「青山霊園33 江藤新平と交わった人たち」
東京の中の佐賀「青山霊園33 高木背水・江藤淳」
東京の中の佐賀「青山霊園32 鍋島藤蔭・幹」
Posted by 佐賀城本丸歴史館 at 08:00
│東京の中の佐賀