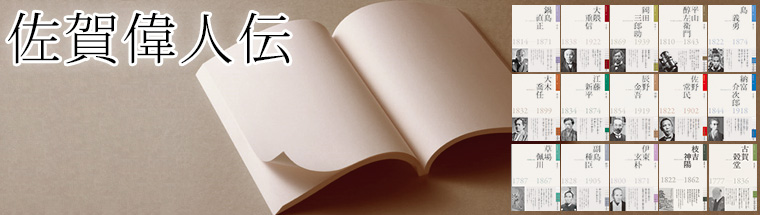2012年12月06日
東京の中の佐賀「東上野・源空寺」
東上野・源空寺
上野駅の東側一帯は、現在東上野と呼ばれています。かつては浅草側の浅草区と、上野側の下谷区に分かれていました。
この地域には、お寺がたくさんあります。
その一つに源空寺があります。
源空寺は、浄土宗のお寺で、五台山文殊院と号し、天正18年(1590)湯島に草創したそうです。

このお寺の特徴は、道を挟んで南側にある墓地に、国や都の史跡となっている著名人の墓があることです。
伊能忠敬は、日本の正確な地図を測量、制作しました。佐賀にも何度か来ています。
国の史跡に指定されています(写真)。

そのほか、天文学者で寛政暦を作った高橋至時(国史跡)や、至時の子高橋景保(都史跡)、文人画で有名な谷文晁(都史跡)の墓もありました。
そうした墓の一つとして、幡随院長兵衛の墓があります。
長兵衛(1622-1657)の父塚本伊織は、もと、唐津藩の武士(一説に、東松浦地方を領していた松浦党の盟主波多三河守の家来)で、子の伊太郎(後の長兵衛)を連れて江戸に向かいました。しかし、伊織は旅の途上下関で病死してしまいます。
伊太郎は父の意志を継ぎ、江戸に出ました。その時頼ったのが、浅草にあった幡随院というお寺だったと言うことです。

長兵衛は、縁あって江戸で口入れ屋を営んでいましたが、乱暴を働く水野家の旗本奴と対立し、敢然と立ち向かいました。しかし、はかりごとにより惨殺されたということです。
長兵衛の生きざまは、江戸でもてはやされ、歌舞伎や講談にも取り上げられました。また江戸の侠客の元祖とも言われています。
長兵衛の墓も都の史跡に指定されています。
墓地蔵は二基立っていて、左側の墓の方に「幡随意長兵衛墓」と彫られています。慶安3年(1650)、紺屋町の西脇惣兵衛というものがこの墓を建てたようです。

以前に来た時は気付かなかったのですが、墓の後に隠れるように小さな仏像が建っていました。

ちょっとほほえましく感じました。
背中に昭和十九年十二月十七日と刻まれていました。

長兵衛の名の由来となった幡随院は、近年まで源空寺の西側にありました。
明治11年の郡区町村編制法により、下谷区と浅草区が誕生する時、その境が現在源空寺の東側を走る清洲橋通りで分けられたのですが、幡随院長兵衛は浅草でなくてはいけないということで、幡随院のある神吉町は、浅草区とされたということです。
 ぷらす1
ぷらす1
幡随院は、徳川家康が江戸開幕にあたって、京都の浄土宗知恩院33世住持・幡随意を開山として招聘し、江戸神田に創建した寺だそうですが、度々の火災などで、場所を転々としました。
昭和15年に、小金井市の現在地に移転しています。何か長兵衛に関わるものがないか探しましたが、見つかりませんでした。


 ぷらす2
ぷらす2
幡随院長兵衛の誕生地は、唐津市相知町大野にあります。この碑は、昭和5年に建てられたものです。棹石だけで6.3mの長さがありますが、セメントなどは一切用いていないけれども、倒れたことがないということです。

上野駅の東側一帯は、現在東上野と呼ばれています。かつては浅草側の浅草区と、上野側の下谷区に分かれていました。
この地域には、お寺がたくさんあります。
その一つに源空寺があります。
源空寺は、浄土宗のお寺で、五台山文殊院と号し、天正18年(1590)湯島に草創したそうです。

このお寺の特徴は、道を挟んで南側にある墓地に、国や都の史跡となっている著名人の墓があることです。
伊能忠敬は、日本の正確な地図を測量、制作しました。佐賀にも何度か来ています。
国の史跡に指定されています(写真)。

そのほか、天文学者で寛政暦を作った高橋至時(国史跡)や、至時の子高橋景保(都史跡)、文人画で有名な谷文晁(都史跡)の墓もありました。
そうした墓の一つとして、幡随院長兵衛の墓があります。
長兵衛(1622-1657)の父塚本伊織は、もと、唐津藩の武士(一説に、東松浦地方を領していた松浦党の盟主波多三河守の家来)で、子の伊太郎(後の長兵衛)を連れて江戸に向かいました。しかし、伊織は旅の途上下関で病死してしまいます。
伊太郎は父の意志を継ぎ、江戸に出ました。その時頼ったのが、浅草にあった幡随院というお寺だったと言うことです。

長兵衛は、縁あって江戸で口入れ屋を営んでいましたが、乱暴を働く水野家の旗本奴と対立し、敢然と立ち向かいました。しかし、はかりごとにより惨殺されたということです。
長兵衛の生きざまは、江戸でもてはやされ、歌舞伎や講談にも取り上げられました。また江戸の侠客の元祖とも言われています。
長兵衛の墓も都の史跡に指定されています。
墓地蔵は二基立っていて、左側の墓の方に「幡随意長兵衛墓」と彫られています。慶安3年(1650)、紺屋町の西脇惣兵衛というものがこの墓を建てたようです。

以前に来た時は気付かなかったのですが、墓の後に隠れるように小さな仏像が建っていました。

ちょっとほほえましく感じました。
背中に昭和十九年十二月十七日と刻まれていました。

長兵衛の名の由来となった幡随院は、近年まで源空寺の西側にありました。
明治11年の郡区町村編制法により、下谷区と浅草区が誕生する時、その境が現在源空寺の東側を走る清洲橋通りで分けられたのですが、幡随院長兵衛は浅草でなくてはいけないということで、幡随院のある神吉町は、浅草区とされたということです。
 ぷらす1
ぷらす1
幡随院は、徳川家康が江戸開幕にあたって、京都の浄土宗知恩院33世住持・幡随意を開山として招聘し、江戸神田に創建した寺だそうですが、度々の火災などで、場所を転々としました。
昭和15年に、小金井市の現在地に移転しています。何か長兵衛に関わるものがないか探しましたが、見つかりませんでした。


 ぷらす2
ぷらす2
幡随院長兵衛の誕生地は、唐津市相知町大野にあります。この碑は、昭和5年に建てられたものです。棹石だけで6.3mの長さがありますが、セメントなどは一切用いていないけれども、倒れたことがないということです。

東京の中の佐賀「おわりに」
東京の中の佐賀「品川台場」【最終回】
東京の中の佐賀「雑司ヶ谷 納富介次郎」
東京の中の佐賀「青山霊園33 江藤新平と交わった人たち」
東京の中の佐賀「青山霊園33 高木背水・江藤淳」
東京の中の佐賀「青山霊園32 鍋島藤蔭・幹」
東京の中の佐賀「品川台場」【最終回】
東京の中の佐賀「雑司ヶ谷 納富介次郎」
東京の中の佐賀「青山霊園33 江藤新平と交わった人たち」
東京の中の佐賀「青山霊園33 高木背水・江藤淳」
東京の中の佐賀「青山霊園32 鍋島藤蔭・幹」
Posted by 佐賀城本丸歴史館 at 08:30
│東京の中の佐賀